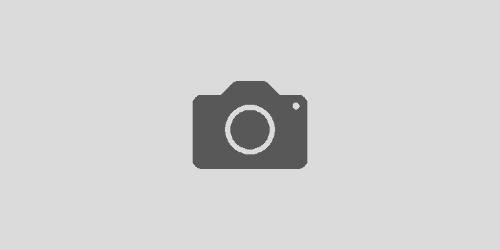前にも書いた気がする【感想】ディアスポラ
2018年に亡くなった勝谷誠彦氏の純文学作品。人柄は好き嫌いが分かれる方だったが、文学はどうか。文藝春秋刊、2011年8月5日 第一刷発行(「ディアスポラ」と「水のゆくえ」の2編収録)
概要
ディアスポラ
中国公安の監視を受けながらも、わずかに残された独自の文化・風習を守り続ける民族が暮らすチベット高原。
そんな荒涼とした高原で、ある「事故」をきっかけに祖国を追われた日本人が避難生活を始めることになる。
高山病と闘い、中国公安・漢人との関係に怯え、地元チベット民との距離感をはかりかねる。
他の国・地域に避難させられた人々はどうなったのか、日本政府は機能しているのか。
何よりも、いつか日本に帰ることは出来るのか、今の生活はいつまで続くのか。
小さなコミュニティの中、各々が様々な不安を抱えながらも日々眼前の希望を探し、ひたすらその日の「命」を全うする。
自身も日本人でありながら、国連嘱託職員という立場で日本人コミュニティとは一定の距離を取らざるを得ない主人公は、この現状にどう立ち向かい何を思うのか。
水のゆくえ
ある「事故」による影響で、全土に避難命令がだされた日本。
その避難命令に逆らい、今も元の土地で生活を続ける人がいた。
山奥も山奥。清流の傍らに位置する小さな村の蔵元も、そんな人の一人だった。
事故の影響でことごとく人が死に、放置された遺体が腐乱臭を放つ。
生き残った人もそのほとんどが避難をしてしまった。
放射能の影響でまともに外出もできず、当然ながら電気・ガス・水道などのライフラインは壊滅、村に残った数少ない人も一人、また一人と鬼籍に入っていく。
そうした中、「事故」が起こる前の生活や村・家が抱えていた問題等に思いを巡らせながら、蔵元は最後の大吟醸造りに取り掛かる。
その大吟醸が出来上がった時、蔵元は何を思うのか。
私的評価
70点。
普段エンタメ小説ばかりを手にする自分には、純文学としての評価は難しい。そもそも純文学というものが漠然としか把握できておらず、その楽しさ、楽しみ方がいまいち掴めていない。
感想
手元の辞書によると、純文学とは「美的情操を訴える文学。興味本位の大衆文学に対して純粋な芸術を志向する文藝作品」とのこと。
となると「芸術とは何か」ということが分からない。
どうも自分には芸術へのアンテナや感度、センスが備わってないよう。
その辺は追々考えて身に付けるとして、
そんな純文学初心者が率直に読後感を一言で表現するなら、
「回りくどくて読みにくかった」
特に、表題作である「ディアスポラ」はなかなかページが進まない。
設定が頭に入ってこない。情景が浮かばない。場面展開に戸惑う。
表現に凝るあまり、スムースな脳内再生が置き去りにされた印象。
特に場面展開は、単なる改行で急に大きく替わってしまう。
スムースに読み進め、「漸く慣れてきたかな」と思った頃に不意に時間・場面が飛ぶ。
数行読み進めてから気づくレベルなので頭の整理と脳内情景の転換にまごついてしまう。
章立てまではしなくとも、空行を一行入れるだけで数段読みやすくなるのに。
これは作家性の問題なのか、編集の問題なのか、自分のスキルのせいなのか。
内容としては、民族意識や国家観、宗教観、原発事故の恐ろしさといった大問題を下敷きにしている点、テレビで見ていた勝谷誠彦氏らしい素材だなと思う程度。
芸術性という点に関しては、情感に心を揺さぶられることはなかった。
感嘆するような美しい表現もほとんどなく、時折「面白い表現したな」と思う程度。
ただただ、勝谷氏の「純文学作品が書きたい」という情念が過剰になっている印象のまま読了。
その点、「水のゆくえ」の方が圧倒的に読みやすい。
日本酒への造詣が深い勝谷氏ならではの作品で、少しホッとする。
「水のゆくえ」のおかげで、「読んで良かった」とは言い切れないものの「時間を損した」 と思わずに済んだ一冊。
ところで、「ディアスポラ」の初出が文學界2001年8月号、「水のゆくえ」は同2002年6月号。
どちらの作品にも共通しているのが、「原発事故により日本人が日本に住めなくなった」という設定。
福島の原発事故の10年余り前の作品だが、今これを読んだ人はどうしても福島を思わずにはいられないだろう。
自分は原発に対して是非の意見を持っておらず、反原発でデモをする人間には、自分の信じる正義に対して盲目過ぎる態度や、往来での邪魔さ加減、論点のすり替え、便乗感があり過ぎて殺意を覚えるものの、正直他人事という意識。
だからといって原発推進派を応援・擁護するつもりもなく、「で?」といった程度。
無関心。
そんな自分でも原発について考えさせられる。
なんてことはなく、日本人としての民族意識やアイデンティティーの置き場所・立ち位置を考えさせられるに留まった。
いずれにせよ、「右も左もよく釣れる」作品ということだけは間違いないでしょう。
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/19a666b7.a1ee920f.19a666b8.d78bf1a5/?me_id=1278256&item_id=13648602&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F4460%2F2000001834460.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)